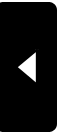2016年11月28日
Lodge Shelter-Ⅱ
先週末、「ロッジシェルターⅡ」の試し張りをしてきました (o ̄∀ ̄)ノ”
本当は週末に実践投入したかったのですが
あいにく日曜日は雨予報
時間をかけて設営をし
写真を撮ったら撤収開始
周囲の方々の不審なまなざしの中 (笑)

届いたのはもう2週間ほど前になります 
宅配のお兄さんが重そうに車から降ろしました
この状態で26㎏超
大の男でも抱えて持ち上げるのはとても重い (笑)

宅配のお兄さんが重そうに車から降ろしました
この状態で26㎏超
大の男でも抱えて持ち上げるのはとても重い (笑)



「箱」を開封するとまた「箱」が 
上段にはポールと収納袋が入っています
これだけで16.35㎏
ポールはロッジシェルターに比べると4㎏弱重くなっています
「ひさし」の部分だけでそれほど重くなっているとも思えませんが

上段にはポールと収納袋が入っています
これだけで16.35㎏
ポールはロッジシェルターに比べると4㎏弱重くなっています

「ひさし」の部分だけでそれほど重くなっているとも思えませんが


ポールを取り除くと更に「箱」が・・・
ほとんどマトリョーシカ状態です
下段の箱には「幕体」が入っていました
他にペグ類なども同梱されています
これが10kg近く
幕体もロッジシェルターに比べると1㎏超増えています
「ひさし」やサイドの分割に伴うファスナー類の重さでしょうか
ほとんどマトリョーシカ状態です

下段の箱には「幕体」が入っていました
他にペグ類なども同梱されています
これが10kg近く
幕体もロッジシェルターに比べると1㎏超増えています
「ひさし」やサイドの分割に伴うファスナー類の重さでしょうか
場所は香川県中部を流れる「土器(どき)川」の河川敷
「ことなみ土器どき広場」
「ドキドキ」しながら到着しました
それにしてもいい天気の土曜日
今夜から になるとは信じられないくらいです
になるとは信じられないくらいです
「ことなみ土器どき広場」

「ドキドキ」しながら到着しました

それにしてもいい天気の土曜日

今夜から
 になるとは信じられないくらいです
になるとは信じられないくらいです到着して荷物を降ろして開封です 
実はこの時まで箱から出したままで放置 (笑)
何が入っているのか見ていません
トリセツを見ながら内容を確認します
幕体(1)・ライナーシート(1)
軒フレーム(3)・ひさしポール(3)・合掌フレーム(6)
脚長フレーム(4)・脚短フレーム(2)・張り出し用ポール(2)
スチールピン・ハンマー・張り綱(8)
が入っています

実はこの時まで箱から出したままで放置 (笑)
何が入っているのか見ていません

トリセツを見ながら内容を確認します
幕体(1)・ライナーシート(1)
軒フレーム(3)・ひさしポール(3)・合掌フレーム(6)
脚長フレーム(4)・脚短フレーム(2)・張り出し用ポール(2)
スチールピン・ハンマー・張り綱(8)
が入っています

今回は試し張りなのでトリセツ通りに設営します
それにしても、そこそこのお値段の幕ですが
ペラペラの説明書、しかも2色刷り (爆)
それにしても、そこそこのお値段の幕ですが
ペラペラの説明書、しかも2色刷り (爆)

整地された地面にフレームを配置します 

この時「注意点」が2点ほど
「軒フレーム」前面部にはそれぞれシールが張られています
シール矢印の方向が「前」になります
併せて「左」「中」「右」の指示が書いていますが
これは幕の外側(写真矢印方向)から見て「左」「中」「右」になります
「軒フレーム」前面部にはそれぞれシールが張られています
シール矢印の方向が「前」になります
併せて「左」「中」「右」の指示が書いていますが
これは幕の外側(写真矢印方向)から見て「左」「中」「右」になります


もう1点は「脚」フレーム
脚フレームには「長」と「短」があります
「脚短」と書かれたフレームが内側の脚になります
脚フレームには「長」と「短」があります
「脚短」と書かれたフレームが内側の脚になります
最初に「合掌」部分の組み立てです 




ジョイント部分です
ロッジシェルターに限らず多くのロッジテントで
プラ製のジョイントにポールを差し込む方式がとられています
ジョイントの奥までポールを差し込んで
回転させれば「バネ」がカチッと穴から飛び出します
これをきちっとしておかなければ
幕が倒壊したり、強風でジョイントが破損する原因になります
ロッジシェルターに限らず多くのロッジテントで
プラ製のジョイントにポールを差し込む方式がとられています
ジョイントの奥までポールを差し込んで
回転させれば「バネ」がカチッと穴から飛び出します
これをきちっとしておかなければ
幕が倒壊したり、強風でジョイントが破損する原因になります
「脚」の組み立てです 
脚はそれぞれ3分割にされています
トリセツでは一番下側の脚を折って設営していますが
ソロで設営する場合や背のあまり高くない方は
下から2番目を折った方が作業がし易いです

脚はそれぞれ3分割にされています
トリセツでは一番下側の脚を折って設営していますが
ソロで設営する場合や背のあまり高くない方は
下から2番目を折った方が作業がし易いです
幕をかけずにテンションがかかっえていない状態だと
フレームの位置がよく解ります
真ん中の2本は真っ直ぐ下に下りていますが
外側の4本は外向きに開いています
「脚長」と「脚短」を分けている所以です
フレームの位置がよく解ります
真ん中の2本は真っ直ぐ下に下りていますが
外側の4本は外向きに開いています
「脚長」と「脚短」を分けている所以です



「ライナーシート」の取り付けです
これからの時期
天井に発生した結露が直接落ちてくるのを防ぐためにも
ライナーシートは必需品です

ライナーシートに付けられている「S字フック」を
ジョイント部分の穴に引っ掛けます
併せて裾の6ヶ所にはプラフックが取り付けられているので
フレームに固定します

トリセツではこの時点で
ライナーシートのS字フックとプラフックを全て取り付ける様になっていますが
ソロ設営の場合や
「屋根タタミ」と呼ばれる撤収方法をした幕では
この時点ではライナーシートの裾の部分は取り付けせずに
尾根部分だけを吊り下げた方が作業が捗ります
そして設営完了後に裾は留めた方が作業し易いです
ライナーシートのS字フックとプラフックを全て取り付ける様になっていますが
ソロ設営の場合や
「屋根タタミ」と呼ばれる撤収方法をした幕では
この時点ではライナーシートの裾の部分は取り付けせずに
尾根部分だけを吊り下げた方が作業が捗ります
そして設営完了後に裾は留めた方が作業し易いです
「幕体」を被せます (o ̄∀ ̄)ノ”
従来のロッジシェルターでは
前方(Dドア)と後方(観音開き)との区別が解り辛かったのですが
Ⅱでは「ひさし」用の幕が付いているので判別がし易いです
従来のロッジシェルターでは
前方(Dドア)と後方(観音開き)との区別が解り辛かったのですが
Ⅱでは「ひさし」用の幕が付いているので判別がし易いです




「ひさし用ポール」の取り付けです 
「ひさし」の付け根部分に穴が3ヶ所開いています
この穴をジョイントに併せて
ひさし用のポールを差し込みます
この時、ひさし用のポールは他のポールと違い固定はされません
ジョイントの穴にバネが入っていて
強い力が加わるとひさし用のポールが中に入り
余分な力を逃がす構造になっています
ひさし用幕の縫製部分を保護する為と思います
左右のひさし用ポールの部分には幕にマジックテープが付いているので
ポールを留めて幕のズレを防ぎます

「ひさし」の付け根部分に穴が3ヶ所開いています
この穴をジョイントに併せて
ひさし用のポールを差し込みます
この時、ひさし用のポールは他のポールと違い固定はされません
ジョイントの穴にバネが入っていて
強い力が加わるとひさし用のポールが中に入り
余分な力を逃がす構造になっています

ひさし用幕の縫製部分を保護する為と思います
左右のひさし用ポールの部分には幕にマジックテープが付いているので
ポールを留めて幕のズレを防ぎます

前後の天頂部分の幕の位置を調整しながら
折りたたんでいた「脚」を伸ばします
脚フレームが幕の「縫い目」に沿う様に幕の位置を調整します
*この時点で天頂部分の幕のズレを直しておかないと設営後もズレたままになります
折りたたんでいた「脚」を伸ばします
脚フレームが幕の「縫い目」に沿う様に幕の位置を調整します
*この時点で天頂部分の幕のズレを直しておかないと設営後もズレたままになります



「幕の固定」です
脚の「石突」部分を
幕裾の固定用テープの「はとめ」に差し込みます
脚の「石突」部分を
幕裾の固定用テープの「はとめ」に差し込みます


固定用テープは長さが調節出来る様になっています
あらかじめ長めに伸ばしておくと次の作業がし易くなります
あらかじめ長めに伸ばしておくと次の作業がし易くなります



角を調整し、脚ポールが幕の縫い目に沿う様に
位置を調整したら幕をペグダウンします
先ほど長めに伸ばした固定用テープを併せて締め込みます
これで幕全体に張りが出ます
ペグの位置ですが
これまでの作業や幕体の重みで石突部分は外側へ開いていると思います
ジョイント部分に余分な付加がかからない様にする為にも
気持ち内側へ石突を戻してペグダウン
ペグは他の幕でもそうですが
対角に打ってゆくのが基本です
また裾ゴムのペグダウンも忘れずに
位置を調整したら幕をペグダウンします

先ほど長めに伸ばした固定用テープを併せて締め込みます
これで幕全体に張りが出ます

ペグの位置ですが
これまでの作業や幕体の重みで石突部分は外側へ開いていると思います
ジョイント部分に余分な付加がかからない様にする為にも
気持ち内側へ石突を戻してペグダウン

ペグは他の幕でもそうですが
対角に打ってゆくのが基本です
また裾ゴムのペグダウンも忘れずに

ペグダウンを終えた状態です

シワがよっていますが・・・(≧∇≦)ノ彡 バンバン!
言い訳(メッシュとアウターが2重になっている部分です)

無風状態ならばこれで設営完了です
ただし、張り綱をしていないので風には弱いです

構造上ロッジテントはドームテントに比べ
強風に弱いと思います
設営時には無風でも夜半に強風へと変わる事がよくあります
張り綱は小まめにしましょう

私は過去に痛い目に逢った経験者です (笑)



ロッジシェルターには他のメーカーに比べ5㎜と太目の張り綱が付いています
幕体の耳(6ヶ所)に通して固定をします
幕体の耳(6ヶ所)に通して固定をします
設営完了です (o ̄∀ ̄)ノ”
幕の設営サイズは
長さ460㎝×幅350㎝×高さ210㎝
フライ部分の素材はポリエステル(耐水圧1800㎜)
幕の設営サイズは
長さ460㎝×幅350㎝×高さ210㎝
フライ部分の素材はポリエステル(耐水圧1800㎜)
従来のロッジシェルターとの一番の違いは
この「ひさし」部分です
幕裾が外側へ張り出している分
雨天時には中まで雨が入ってきました
ひさしをつける事で雨の進入が幾分緩和されます
この「ひさし」部分です
幕裾が外側へ張り出している分
雨天時には中まで雨が入ってきました
ひさしをつける事で雨の進入が幾分緩和されます
そしてサイドの張り出しパネルが両サイド共に
「2分割」された事です
これにより設営時に細かな対応が取れます
「2分割」された事です

これにより設営時に細かな対応が取れます
室内です 
入り口は前方が「Dドア」、後方が「観音開き」
外側がアウター、内側がメッシュの2重構造です
これは従来のロッジシェルターと同じです
Ⅱは内側のメッシュも2分割になっています

入り口は前方が「Dドア」、後方が「観音開き」
外側がアウター、内側がメッシュの2重構造です
これは従来のロッジシェルターと同じです

Ⅱは内側のメッシュも2分割になっています
フルメッシュにして張り出しを使った常態です
張り出し用のポールと張り綱は付属しています
真夏のスタイルですね~
張り出し用のポールと張り綱は付属しています
真夏のスタイルですね~

フルオープンの状態です 
屋根と柱のみ
私ならレクタタープを張ります (笑)

屋根と柱のみ
私ならレクタタープを張ります (笑)
巻き上げた幕のオガワらしい留め方
防滴のライナーシート
ファスナー部分を覆うフライシート
さすが長年ロッジテント手がけてきた老舗メーカーの作りです
防滴のライナーシート
ファスナー部分を覆うフライシート
さすが長年ロッジテント手がけてきた老舗メーカーの作りです

ずっと以前、snowpeakのリビシェルを購入した時に
どちらにするか迷いました
当時は積載の関係でリビシェルにしましたが
念願がかない我が家にやってきました
問題は1号2号がキャンプにあまり来てくれない事 (笑)
当分はグルキャン用の宴会幕になりそうです (≧∇≦)ノ彡 バンバン!
おわり

Posted by あお. at 09:10│Comments(0)
│OGAWA CAMPAL
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。